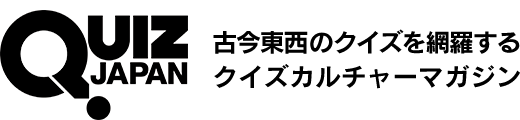伝説の『第13回アメリカ横断ウルトラクイズ』に集う若きクイズ王たちの青春を、気鋭のライター「てれびのスキマ」(戸部田誠)が描く話題沸騰のノンフィクション小説『ボルティモアへ』。時代は1987年、RUQS怒涛の快進撃が始まる!

『ボルティモアへ』目次
第0回 連載開始予告
第1回 消えた天才
第2回 『ウルトラクイズ』の衝撃
第3回 レスポンスタイム
第4回 宝の地図
第5回 前哨戦
第6回 ハチマキ娘
第7回 ニューヨークで踊る男
第8回 奇跡の会合
第9回 クイズサークル
第10回 昭和40年男
第11回 マイコンボーイ
第12回 伝説のテストマッチ
第13回 立命オープン
第14回 RUQS革命
第15回 聖地 フラワー
第16回 トリビアル・パスート
第17回 地獄の細道
第18回 クイズ列車
第19回 ポロロッカ
第20回 エンドレスナイト
第21回 大阪大学“RUQS”学部
第22回 ハイキングクイズ
第23回 玉屋
第24回 coming soon…
(以降、毎週木曜日公開予定)
Ⅵ 長戸勇人、22歳。挫折
玉屋
「おっさん、まだ残ってるぞ」
立命館大学のサークル用の掲示板にはそんなメモが貼られていた。
1987年9月のことだ。
『第11回アメリカ横断ウルトラクイズ』でRUQS初代会長の稲川良夫が見事予選を突破し、ウルトラクイズのツアーに参加していた。その戦況の情報が随時サークルにもたらされ、それがRUQSのメンバーだけがわかる短い言葉で掲示板に書かれ、情報を共有していたのだ。
稲川良夫はこの年、社会人1年目。RUQSは既に引退していたが、『第11回ウルトラ』の予選でも、揃いの黄色いTシャツを着てRUQSの面々と一緒に参加した。
来年には東京ドームが完成するため、後楽園球場で行われる最後の1次予選だった。
第1問の「ニューヨークの自由の女神は、大統領から名誉市民の称号を受けている」という問題に、歴代チャンピオン全員が「○」を選択。しかし、正解は「✕」という波乱で幕を開けた。
RUQS勢は「✕」を選択し生き残った。
「『た~まや~』のかけ声でおなじみ江戸花火の玉屋は火事で店を潰した」
この問題に多くの出場者は「✕」に走った。
RUQS勢の多くもそうだった。
だが、稲川良夫は違っていた。
なぜか「○」に行かなくてはならない気がした。
そんな不思議な力に導かれて、RUQSから離れて「○」を選択したのだ。「○」を選んだのは147人、「✕」は378人。
正解は「○」。
一気に3分の1以上が淘汰された。
結局、この問題でRUQS勢は、稲川と鎌田弘を除いて“大量虐殺”されてしまったのだ。
ちなみにこの頃、RUQSの初代早押し機が酷使し続けたため4人用のボタンのひとつが大破してしまった。いきなり「パン!」という音とともにボタンが吹っ飛び天井に激突してしまったのだ。その光景と『第11回』のこの問題とを重ね、初代早押し機が「玉屋」と呼ばれるようになった。
稲川と鎌田はそのまま1次予選を通過した。『第10回』の瀬間に続くRUQSからの予選通過者だった。
けれど、稲川は複雑な心境だった。
まさに社会人1年目の稲川はそれに当たっていた。ツアーは最後まで勝ち残れば最長1ヶ月近くに及ぶ。就職した凸版印刷は一部上場の大手企業。多忙で簡単に休みなどとれるはずもなかった。しかも、社会人1年目だ。わがままを言えるような立場ではなかった。
後楽園の予選は1日だけのお祭りのようなもの。出るだけ出て、もし通過しても、予選突破者に出されるという「勝者弁当」だけ記念に食べて、辞退しようと思って参加したのだ。
しかし、実際に通過すると、「やっぱりどうしても行きたい」という思いが強くなっていく。
引き裂かれるような思いだった。
予選からツアー開始までの猶予期間の3週間、稲川は悩み抜いた。
「1枚目だけコピーしてくれ」
稲川が上司に3枚にわたって書かれたツアーの予定表を見せながら相談すると、上司はそう言った。「有給休暇の範囲だったら行ってもいい」という答えだった。新入社員に与えられていた有給休暇は6日間。ちょうど予定表の1枚目までで帰ってくればギリギリ有給休暇内でおさまる。
「それ以上休むと、キミの将来に良くないからね」
その一言が稲川の胸に重く突き刺さった。
でも、行ったら戻ってこないだろうな――。
そんな確信があったがゆえに、余計に思い悩み、稲川は「辞表覚悟」でツアーに向かったのだ。
どんな相手と対戦し、どんな手を出して、どういう風に負けたのか、まったく記憶がなくなるほど、頭の中が真っ白になった。
ふと、横を見ると鎌田弘も敗者席に座っている。
ああ、辞表まで覚悟してやってきたのに、もう終わってしまうのか……。
稲川は天を仰いだ。
「敗者とはなられましたけども、ここまで来られたわけですし……」
じゃんけんの敗者を前に慰めるように徳光和夫は話し始めた。
「わたくしも11年間『ウルトラクイズ』をやってまいりまして、今回ある権利を取得いたしました」
そう徳光が言うと、「おーー!」と敗者たちは歓喜した。復活できるチャンスがあるかもしれない。稲川も喜びを爆発させた。
「獲得した権利。みなさん全員を飛行機に乗せます! そして勝者より先に成田から飛び立ちます。行く先はみなさんの期待を決して裏切らないところであります」
なんと敗者が先に飛行機に乗るという。どういうことだ? と疑問を挟み込む余地もなく徳光がシュプレヒコールをあげる。
「俺たちが勝者だ!」
敗者たちがそれに続く。
「俺たちが勝者だ!」
地元にほど近く、よく訪れていた名古屋の街の風景があらわれたのだ。
一行は「名古屋縦断ミニトラクイズ」と呼ばれる『ウルトラクイズ』の自己パロディ企画に参加。最後に辿り着いたのがパチンコ「ニューヨーク」だった。
まずクイズが出題され、その正解者に200発のパチンコ玉が与えられる。それを使ってパチンコで2000発を出した者から先着7名が「敗者復活」できるというルールだった。
稲川は「ぜひ名古屋弁でお答えください」という徳光の前フリで、きっと「エビフリャー」が答えの問題が出ると直感した。
第1問目、いきなりその予感通り「タモリの昔のギャグで名古屋の人が一番のご馳走だと思っているものは?」という問題が出た。すかさず早押しし正解。真っ先にパチンコ台へと向かった。
実は稲川は幼い頃からパチンコ店によく通っていた。今では絶対に許されないが、当時は緩く、おばあちゃん子だった稲川はギャンブル好きの祖母に連れられ店で玉拾いをしたり、店員に遊んでもらっていたりしていたのだ。その影響もあって、大学生になってもよくパチンコに行ってはいたが、決して強くはなかった。
だが、この日、台を決めて打ち始めるといきなり大当たり。ドル箱いっぱいに3499発の出玉を持って最初に復活を果たしたのだ。
「ばあちゃんが導いてくれて勝ち抜けたんだな――」
稲川は1年前に亡くなった祖母を思った。
稲川がツアーに出発する少し前、長戸勇人から手紙が届いた。
そこには長戸がこれまで『ウルトラクイズ』を研究してきた成果がびっしりと綴られていた。
そこに書かれたノウハウ以上に、その気持ちに稲川は感激した。何度も読み返し、大きな心の支えになっていた。
もちろん、長戸が導き出した“秘策”も役に立った。
稲川は「なるほど」と得心した。だが、番号を選ぶ段になって困惑した。番号が40番までしかないのだ。一瞬パニックになったが、冷静に「32」以上の番号を選ぼうと考えた。「31」までは誰かの誕生日である可能性があるからだ。
すると、思ったとおり簡単な問題を引き当てた。
正解を確信し、内心大喜びして「✕」に向かって走り出した。
スタートして思い出した。スタッフから「必ずメガネを外すように」と言われていたことを。けれどもう止まることはできない。
迫りくる「✕」の壁。「高く飛び上がると危険だから、野球のヘッドスライディングのように飛び込め」というスタッフのデモンストレーションがまるで走馬灯のように頭をよぎったが、興奮した体は言うことを聞かなかった。
高く飛び上がった稲川の体はボードを勢いよくぶち破った。
危ない!
稲川がそう感じた刹那、「パン!」と破裂し激突した「玉屋」のボタンのように、そのまま急角度で顔からマットに突っ込んだ。その勢いで、下半身はエビ反りに。激しく腰を痛めてしまった。
そんな「一生もの」の傷と引き換えに、稲川は次のチェックポイントのハワイも勝ち抜き、いよいよ有給休暇のリミットである6日目が近づいてきていた。
(第24回に続く)
- 『ボルティモアへ』バックナンバー
第0回 連載開始予告
第1回 消えた天才
第2回 『ウルトラクイズ』の衝撃
第3回 レスポンスタイム
第4回 宝の地図
第5回 前哨戦
第6回 ハチマキ娘
第7回 ニューヨークで踊る男
第8回 奇跡の会合
第9回 クイズサークル
第10回 昭和40年男
第11回 マイコンボーイ
第12回 伝説のテストマッチ
第13回 立命オープン
第14回 RUQS革命
第15回 聖地 フラワー
第16回 トリビアル・パスート
第17回 地獄の細道
第18回 クイズ列車
第19回 ポロロッカ
第20回 エンドレスナイト
第21回 大阪大学“RUQS”学部
第22回 ハイキングクイズ
1978年福岡県生まれ。お笑い、格闘技、ドラマなどを愛する、テレビっ子ライター。「週刊文春」「水道橋博士のメルマ旬報」などで連載中。主な著書に『タモリ学』『コントに捧げた内村光良の怒り』『1989年のテレビっ子』『笑福亭鶴瓶論』『全部やれ。日本テレビ えげつない勝ち方』がある。