誰のためでもなく
クイズのためのクイズの本を書きたかった
――それにしても、これをタレント活動と社長業をやりながら書くっていうのがホントにすごいと思いますよ。
伊沢 これは何の気取りもなく地獄でした(笑)。
――だって『アイ・アム・冒険少年』で無人島に行ったりするわけじゃない。
伊沢 そうですね。無人島に行く飛行機で書いてました(笑)。無人島に行くと2日活動ができないから。
――連絡も取れなくなる(笑)。
伊沢 そうなんですよ。だから行きと帰りの飛行機で書くしかなくて。それと、これを書き始めた頃に「QK-go」という各地に講演会をしに行くイベントを「QuizKnock」でやっていて、その移動時間は、飛行機だとWi-Fiが通じないので、そこが一番落ち着いて書けてました。そんな感じで、ずっと合間合間で書き続けました。まあ会社の業務の移動時間は業務時間ではありますけど、基本は業務時間外で、会社が終わって、もしくはタレントの仕事が終わって、家に帰ってきて、「テレビを見るか」ってところを我慢してこれを書く、というのを毎日2時間。でも「毎日は無理です」と。「2日に1回にしてください」って言って。
――壮絶ですね……。
伊沢 締切もどうしようもなかったんで、3日単位とかで切ってもらったんですよ。僕の予定を全部編集の松浦さんに提出して。で、「これまでにここ、これまでにここ」って、すごいスモールステップで書いていきました。1回完成するまでは1年以内で終わったんですけど、そこから書き直しで1年以上かかったので。いやー、つらかったー。
――『勉強大全』もすごいなと思ったけど、よくこの内容を1年半で書きましたね。
伊沢 ホントに後期青春がこれでぶっ飛びましたね。25歳から27歳の楽しく遊べる時間に休日も遊びに行かず。まあサッカーはめっちゃ見てますけど(笑)。だから、いまだに芸能界っぽい友人がほとんどいないのはこの本のせいかもしれない。……いや、もともと友達少なかったので自分のせいですね(笑)。ただ、コロナがあって全く飲みにも行かなかったので、集中して執筆できたのはありました。だから……ようやく解放されますね。でも、ありがたいのは、出版社が2年も待ってくれたことですね。
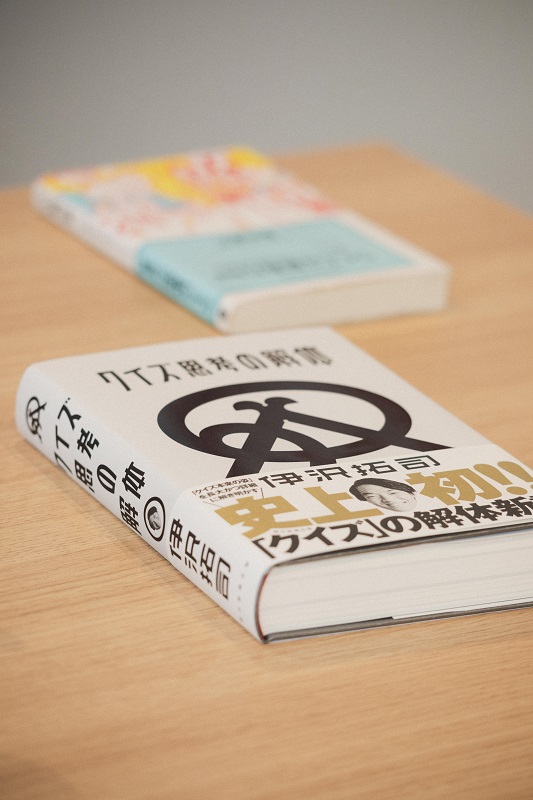
――その話も詳しく聞きたいですね。
伊沢 こんな前代未聞の本を出したことがすごいじゃないですか。売上の見通しも立たないわけで。「誰が手に取るの?」と。かばんにも入らないんですよ、これが(笑)。
――「QuizKnock」の単行本とは真逆ですもんね。
伊沢 そうですね。しっかり読みやすいフォーマットを心がけているのが「QuizKnock」の本で、この本は真逆ですね。だから出版社的にも、ある程度もとが取れるような値段にしなきゃいけないですと。僕も大学の先生に取材に行っているし、資料も大量に出してもらったし、一人の編集者を2年半拘束して毎日のように動いてもらってるわけで。すごくお金がかかっているんです。出版社側の負担と期待……期待じゃないな、ドキドキですよね。不安のほうが大きかったはずです。担当の松浦さんとは時に激しく議論しましたけど、最終的には僕を信じてくれて。1~2日遅れても、「いいものを作るためならしょうがないんで、思いっきりやってください」と。最後は多分諦めも入っていたんでしょうけど、「もう、好きにやって!」っていう感じだったので(笑)。それがなかったら、できてないですね。昨日この本が届いたんですけど、直筆のお手紙が入ってて。そこが感動しましたね。ずーっと二人三脚でやってきて、「これを付き合ってくれたの?」「これを商品化してくれたの?」という感謝は計り知れないですね。
――それも縁ですよね。
伊沢 出版の部のトップの方にご挨拶にも行きましたけど、一つも小言を言われなくて。ちょっと覚悟はしていたんですよ。「いつ終わるんだね」とか言われるのかなと思ったら、「いいよ、やれるかぎりのことをやりなさい」みたいな。本当に素晴らしい編集者の方に会った、そして素晴らしい出版社で出させてもらった。これはもう本当に運がないとできないというか、先方の人徳がないとできない仕事なので。僕が「業務中は書けません」「日が高いうちは僕は原稿が進まないです」って言った時に受け入れてくださった。そんな生意気な著者いないですからね(笑)。
――しかも、まさかこんなボリュームになるとは思ってなかったでしょうね。
伊沢 そうなんですよ。そもそもこうなることを想定して作っていないので。昔の台割を見ると。写真を撮ったのも2年前の『天8』(19年に開催されたクイズサークル対抗の団体戦)の時ですからね。
――そこまでの激務の中で、伊沢君がこの本を書こうと思えた原動力って何だったんですか?
伊沢 今回はクイズのためのクイズの本にしようと思ってて。本を書く時って必ずターゲットを決めるわけですけど、今回は誰のためにというより、「クイズのために書きたいな」と思ったんですよね。クイズがクイズであること。さっき言ったようなレッテル貼りを逃れるというか、クイズの文脈にいる人を除外した状態でクイズが定義されてしまうような状態は避けたかったんですよね。「クイズは広くて浅い」みたいなことを言われてしまうのはもったいない。もちろんその広くて浅さにずっと拘泥して、競技オンリー主義みたいになるのもよくない。でも、現実的に今そういうプレイヤーはあんまりいないと思っていて。今の若手はホントにどんなジャンルでも強いんですけど、そういう人たちの普段の生活なんかを見てると「人生をエンジョイしながらクイズをエンジョイしてるな」って思うんですよね。
――なるほど。
伊沢 だから、クイズで今起こっている現象をちゃんと書けるようにしたい。じゃあ最終的に誰にこの本を届けるかって考えたら、クイズプレイヤーではないなと。クイズプレイヤーは知ってる内容だろうし、彼らもクイズという現象の一部だから、この本も必要ない。逆にクイズに全く興味ない人でもないなと。やっぱり、これからクイズする人とか、クイズに興味ある人、もしくはクイズというものを話題に上げる人にとって、辿るべきものが何もないから「広く浅く」みたいなレッテル貼りが行われるわけで。こういう本が1つあれば、レッテル貼りを回避はできる。じゃあそういう人に届けようと。ラーメンのおいしさを知らない人、ラーメンそのものを知らない人は麺の味のみの批評になってしまうかもしれない。もちもちとかつるつるとかだけになるけど、ホントはラーメンのうま味って、チャーシューだったりスープだったりとかするわけで、実は「スープから飲みましょうね」みたいなことをちゃんと言える本でありたい、っていうふうに思っていたんですよね。
――その例えはわかりやすいですね。
伊沢 だから、このあと別のラーメン屋ができる必要性があるんですよ。別のラーメン屋だったりとか、別のラーメン批評家。(ラーメン評論家の)石神さんの次が出てくる必要があるんですけど、でもこの本があれば、少なくとも「参照すべきものがないから」っていう理由でのレッテル貼りは逃れられるし、最悪この本が書店に並べば、「クイズってそんなに語ることあるんだ」と多少魔除けになるというか、ザコ敵は倒せると思うので(笑)、それは意図はしてましたね。とにかく「クイズ文化というものへの侵犯をされたくないな」というところはモチベーションになっていました。この本がその侵犯を犯す可能性を恐れながら、ですけれど。

――でも、世阿弥の『風姿花伝』のように、どのジャンルでも、その文化を確立した理論書というのは絶対に大事だから。クイズにおいて、それを書けるのは伊沢君だったということで。
伊沢 そうですね。だから自分が書くことへの葛藤はあったし、まさに規格化することへの恐れはあるかもしれないけれど、規格を壊せるだけのポテンシャルは業界にあると思いますし。それこそ「QUIZ JAPAN」が定期的に出ているというのは、歴史が続いていって、歴史の中にこれが位置づけられて、今後批評されていく可能性があるということだし。この本を読んだら、きっと感想を検索すると思うんですよね。特にクイズに関係ない人は、「この本ってどう位置づけられてるんだろう?」ってなるわけで。その時にみんなが書いたnoteとかが出てきたら、めちゃいいなと思ってて。それって知の在り方として、すごい健全ですよね。だから1回、石を投じて、叩き台になろうというのはすごくありました。
――その覚悟もなかなかできないですよ。
伊沢 『踊る大捜査線』の中で、いかりや長介さんの「青島、正しいことをしたければ偉くなれ」っていう名言があるじゃないですか。ブレイクスルーをするためにはそれが必要だなと思うんですよ。物事を動かすためのパワーというのが、この業界を進展させていく上では必要だと思うんですけど、その「偉くなる」っていうのは、世間に認められる肩書きが必要ですねっていうことではなくて。僕自身も実際「クイズプレイヤー」と自分で名乗っているぐらいで「クイズ王」は避けていますし、あんまり肩書き主義にはなりたくはない中で、その「偉くなる」というのは、ポジティブかつ多様な印象を持たれるようになるということなのかなと。要は聞く耳を持たせる、もしくは持たれることが大切なのだから、別に地位によって耳を開かなくても、心の扉さえ開かせてしまえばいい。極論、「いいじゃんいいじゃん、まあ子供のやったことだし」「偉いね、偉いね、よく頑張ってるね」というぐらいの感覚でひとまずは満足していいのかなと。
――なるほど。ステレオタイプな権威としてテレビに使われるんじゃなくて、常に愛されるというか、身近にいる存在ということですね。
伊沢 はい。そうすれば「パーソナルスペースに入れてやってもいいな」とか、もしくは「こいつを他人のパーソナルスペースに解き放ってもいいな」と思ってもらえるようになるんじゃないかと。前者で言ったら見る側が受け入れてくれるってことだし、後者だったらCMに使うとか、コマーシャリズムの中に入っていくことになると思っていて。そこは割り切りをしなきゃいけないと思っています。だからそういうタイプでの偉くなり方が必要なんです。ポジティブなイメージと、「こいつはいろいろできるな」「多様なところで耐えられるな」というイメージ。結果論ではありますけど、テレビ出演や「QuizKnock」を通して、ここは手にすることができたのかなと。これはなにも位が高くなったわけではないので、先程のような「偉い」になる。それができたからこそ、第2のステップとして、これまで見てくれた人に、「今までこうやってテレビで出てこういう解説をしてきたけど、裏にはこういうことがありますよ」っていうことが、ようやく本として出せたと思っています。
――なるほど。「QuizKnock」のイメージにもつながる話ですね。
伊沢 はい。僕は「QuizKnock」第一主義なんで「QuizKnock」が利することは第一だけど、その先にクイズ界を利することができればいいなと思うので。結果それが「QuizKnock」を利することだと思うし。なので、僕が前に出ていきながらある程度保てたと思えるのはクイズ界のおかげです。クイズをやっている人たちがいっぱい考えてくれて、いっぱい歴史を蓄積してくれて、僕に指摘をしてくれたおかげなので。それがあったからこそ、この本になったかなと。もちろんこの本で捨象してしまっている部分というか、結果的に切ってしまった部分というのはどうしても本になる以上はしょうがなかったので申し訳ないですけど。でも、これからも僕は、ポジティブかつ多様な偉くなり方をしたいなと思っていますね。それで呼んでこられる新しい風。それこそ資本力とかも含めてですけど、それらが業界をよりよい方向に向けてくれるのかなと思います。だからこそ「QuizKnock」でイベントもやりますし、そういう形を僕は目指しています。僕もあくまでクイズ界の一員として知恵を絞り続けるので、ぜひこの業界がまた一歩先に進んでいくようなことになっていけばなと思っています。
――伊沢君の次なるステップを期待しています!
