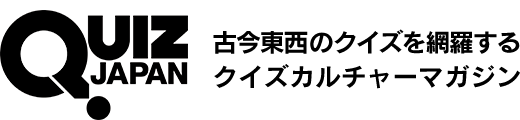メジャーなタレントで数字を獲っても
自分の手柄にはならない
――いろいろなものにドハマりしてきた板川さんですが、その中でも特にゲームへの愛をバラエティ番組の形に昇華されたのが『勇者ああああ』です。この番組はどういうきっかけで生まれたのでしょうか?
板川 番組が立ち上がったのは17年なんですけど、その前年くらいから世の中が「eスポーツ元年」みたいなことを言い始めて。で、会社でも「eスポーツがビジネスになるんじゃないか?」みたいな話がなんとなく出てきたんです。その頃、社内で僕はゲームが相当好きというのは割と有名だったので、「ゲーム番組の枠を作りましょう」ってなった時に、僕が出した企画書に対し「面白いか、面白くないか?」をジャッジできる人間がいなかったんですよ。そこはラッキーでしたね。今の若手のディレクターからすると、「なんであんな板川さんの趣味みたいな番組が通ってんだ?」って疑問だったと思うんですけど(笑)。
――なるほど(笑)。とはいえ、大好きなゲームの番組ということで、企画書はそれなりに力を入れて書かれたのですよね?
板川 最初の企画書の段階では「ふわっとしたことは書くのをやめよう」と思っていて。
――企画書の冒頭に書くテーマみたいなところですね。
板川 はい。なので、コーナーの案とかは、企画書に細かいルールまでしっかり書いてました。例えば「コマンド危機一髪」っていうのは「(『ストリートファイターⅡ』の)波動拳のようなコマンド技をみんなで出し続けて、誰かがミスしたら電流を流す」っていうコーナーなんですけど、こういう「全員で何かをやって、誰かがミスしたら連帯責任で罰ゲーム」みたいな企画って、バラエティ番組でやる「百円ライターをシュッシュと点けてって、誰かが失敗したら全員で罰ゲーム」みたいなのと一緒じゃないですか。要は「バラエティ番組のシステムをゲームに落とし込む」、つまり「のり代」を作るノウハウを僕が一番持ってたってことだと思うんですけど。
――なるほど。
板川 波動拳って、普段はめちゃめちゃ出せるのに、いざ本番になると手が滑って出ないみたいなことがけっこうあるじゃないですか? だから、ゲーム好きな人がその時の企画書を読んだら「あー、なるほど」と思うし、ゲームに興味がない人が読んでも「あー、バラエティのあの感じね。なんとなく画は見えるわ」と思える。そういうコーナーがいくつも作れているのは、そういうことなんだろうなという気がしますね。
板川 そうだと思います。たとえば、オープニングのテレビ東京のロゴが出たりする演出も多分、上の人は何が何やらわかってないと思うんですけど、あれはプレイステーションのロゴが出てくる時と同じような音にして、尺も一緒にしてるんですよ。僕と同じ世代の30代前半から20代後半の人が見たら「あっ、僕らと同じ世代が作ってるんだ」って気づくような「あるある」というか。そういう「気づかれないなら、それでかまわない」「でも、気づいてくれたらうれしいな」っていうぐらいの仕掛けはちょこちょこ作ってましたね。
――『勇者ああああ』は内容もさることながら、キャスティングもなかなか挑戦的ですよね。
板川 はい、ほかではなかなか見ないような人を(笑)。正直、人気者を出して数字をとっても「これ、僕の手柄じゃねえな」と思う時がたまにあって。例えば、小峠(英二)さんとか麒麟の川島(明)さんみたいな「的確なコメント」で笑いがとれる人って、すごい天才だと思うんですよ。でも、僕は「それで撮れ高ができても、スタッフの功績にはならない気がしません?」なんて、どこかで思っちゃうんです。
――なるほど。
板川 最初にその人たちを発掘した人は偉いと思うんですよ。だけど、それ以降は誰かが面白く作ったVTRを観て、それを楽しんだ人が、ただ会議でホワイトボードに名前を書いていくだけじゃないですか。僕がこの番組を始めた頃は多少尖ってたこともあって、それがちょっとだけ嫌だったんですよね。なので「確実に面白い人を連れてくるんじゃなくて、面白そうな人を連れてきて、現場でどうにもならなかった部分は編集で面白くするほうが楽しいんじゃないか」と。それで「まだ知られていないけど、世の中にはこういう人たちがいるんですよ」って広めていくのが本来のディレクターの仕事な気がするんですよ。うちの番組でいうと、ヤマグチクエストだとか、ペンギンズ・ノブオとか……。こんなこと言ったらアレですけど、ペンギンズ・ノブオさんの漫才なんか僕、ひとつも好きじゃないですからね(苦笑)。
――そうなんですね(笑)。
板川 僕の中では、あの人はゲーム芸人っていう立ち位置なんで。なので「僕、あのチンピラの漫才、面白いと思ったことないです」って本人にも言ってます(笑)。ただ、ゲーム愛だけは本物ですけど。
――ネタは認めないけど、ゲーム愛は認めると(笑)。
――おかずクラブのゆいPさんもすごかったですね! コロナの自粛期間にやることがなくて、『ファイナルファンタジーIV』にドハマりしたという。
板川 そうそう。面白いんですよ、あの人! ゲームを始めたばっかだから、そこまで詳しいわけじゃないんですけど、ホントに楽しんでるから、むちゃくちゃうれしそうにしゃべるんですよね。Zoomで打ち合わせしてても、もう「そのまま楽しそうにしゃべってもらうだけで多分、大丈夫だと思います」という感じでしたからね。やっぱり、他人が楽しそうにしゃべってるのは、見ていていい気持ちになるし。何でも語れるヘビーユーザーもいるだろうけど、ただ普通に遊んでるだけのライトユーザーもいると思うんで。
――ヘビーユーザーということでいうと、『アメトーーク!』とかでもテーマによっては、全然知られてない芸人さんがめちゃくちゃ詳しくて面白かったりしますよね。
板川 ありますね。だから、そういう人を探したほうがいいですよね。なのに、「この人を置いときゃ間違いねえだろ」みたいな感じで、けっこう安易なところに行ってしまう人が多いので。
――『勇者ああああ』は、タレントさんに限らず、放送作家の岐部(昌幸)さんとか、本来は裏方であるスタッフの方も割と露出しますよね。
板川 今はYouTubeとかで自分が作った作品をすぐに出せる状況なので、「多少はテレビマンとして自分の名前が世に出るような仕事をしたほうがいいんじゃないかな」って気がするんですよね。一昔前だと、世の中に名前を売ったりするディレクターを「出たがり」って揶揄する状況もあったと思うんですけど、そういうのはなくなってきましたし。僕自身、人前に出るのが平気な人なので、特に思うんですけど。何しろ、うちの会社にはラジオのパーソナリティまでやる先輩がいるぐらいだから(笑)。
――佐久間宣行さんですね。その佐久間さんは、『ゴッドタン』でまだ世に出てなかった芸人を何人も発掘し、ブレイクさせてきたことで有名ですよね。先ほどおっしゃっていた、「最初に見つける」ことの達人というか。
板川 そうです。僕も『ゴッドタン』で3~4年修行してたんで、三四郎がスターになる瞬間を現場で見てたりするんですよ。全く見たことない人が「ドーン!」って笑いとって、また次の収録も呼ばれてる、みたいなのを見てると、そういうのに憧れたりしますよね。「あっ、こういう人たちが売れてくんだな」みたいな感覚というか……。だって、あの時の小宮(浩信)さんって最初、何言ってるかわかんなかったですもん。歯が折れた状態なんで。
――そうでしたね(笑)。
板川 小宮さんが歯が折れて、足を怪我した状態で来てたので、相方の相田(周二)さんは「せっかくのチャンスなのに、なんでそういう状態で現れるんだ」って、ちょっと怒っていたんですよ。でも、スタッフとしては「天才だ」って出てきた芸人が大怪我してる、っていうその感じも含めて超面白いじゃないですか。あれは「芸能人として持ってなんなー」という感じでしたね。で、そうやって自分たちが見つけた人がほかの番組に出てるのを見たりすると、素直にうれしいですよ。
板川 そうですね。まぁ、それはそもそも「ゲーム芸人」という人があんまりいなかったからだと思いますけど。だから、詳しい人が現れると、仕事が集中するようになるんでしょうね。あと、これまでのゲームいじりができる人って、ファミコンあたりのレトロゲームに詳しい人しかいなかったんですよ。それがプレイステーション世代にも出番が回って来たというか。だから90年代の後半とかに出たRPGのことを語れるヤマグチクエストとかペンキンズ・ノブオに仕事があるんだろうなと思うんです。そのへんを語って欲しかった視聴者が、20~30代を中心にけっこういたはずなんで。でも、そこはテレビ界では黙殺されていたというか、気づかれてもいなかったエリアだから。
――確かに「ゲーム芸人といえば有野(晋哉)さん」という時代が15年以上続きましたからね(『ゲームセンターCX』の放送開始は03年)。
板川 10歳年齢が違ったら当然、ハマったゲームだって違うわけで、ようやくそこが更新されたんだろうなという気がしますね。別に「僕らが更新した」とは言いませんよ。でも、その一助は担った気はします。
――マヂカルラブリーの野田クリスタルがエロゲーを語る時の熱量とか、めちゃくちゃ面白いですものね(笑)。
板川 やっぱりエロゲーの文化って面白いんですよ。だって、それこそさっきのクイズと一緒で、一般の人からすると意味わかんないじゃないですか。僕からすると「AV観りゃいいじゃん」と思うんですけど、「なんでわざわざそれを買って、マウスでクリックしてんだ?」っていうその理屈が気になるんですよ。しかも、そこはみんながまだイジってないところなんですよね。お笑いの入口とか下ネタトークの入口として、AVとか風俗の話はめちゃめちゃイジるのに、「エロゲーの話をしてるやつは見たことねえや」みたいな。僕の中では、そういうところから始めて、下ネタというジャンルの中での新しい部分をちょっと作れたらな、というぐらいの感じがあるんですけど。実際に話も面白いですし、「そういう世界があるんだ」っていうのは普通に情報として「へえー」と聞けちゃいますし。ただ、内容に品がなさすぎるので、プライムではあの話はできないですよ。
――なるほど(笑)。
板川 「そこはさすがに……」っていう。だって、現場で聞いていると、ほぼ放送禁止用語しかしゃべってないですから。「いやいや、それテレビわかってねえだろ」という(苦笑)。
――そうですね(笑)。
板川 ただ、僕は別に下ネタはあんまり好きじゃないんですよね。これまでの話からすると、何の説得力もないと思いますけど(笑)。でも、エロゲーに関しては「下ネタの新しい切り口としてこういうのもあるよ」というのを紹介したかっただけなんで。だから、その中で下品な話はあんまりしたくないんですよ。僕も引いちゃうし、基本的には家族みんなで観て、笑ってもらったほうがいいと思っているんで。テレビの前のエロゲー好きな人が「そういうのを話す人が芸能界にもいるんだ」「こういうことがテレビで話されたんだ」という状況さえ理解してもらえたら、この企画は終わりでいいのかないう気はしてます。バイオレンスとかブラックなお笑いは大好きですけど、下品なことはあんまり好きじゃないですから、あまり深追いしたくないんですよね。だって、ハリウッドザコシショウさんの「珍棒」とかも、「下品だから面白い」というよりは、「いい大人がガムテープを模した男性器を腰につけたものを振り回して暴れている」という狂気の部分を笑っているわけじゃないですか。あれって「何してるんだろう、この人?」っていう部分が面白いのであって、「チ○コ」がどうこう言うのが面白いわけではないですよね?
――そうですね(笑)。
板川 僕はどっちかというと、そういう芸人のぶっ壊れている部分とか狂気、あるいはブラックな部分とかで笑わせたいですね。